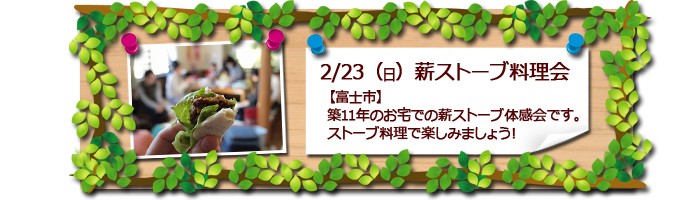厳寒の東北で断熱を勉強しよう その3
昨日の続きです。東北シリーズ最終回。
場所を岩手から秋田に移し、ここで私は度肝を抜かれることになります。

お邪魔させていただいたのは、秋田県大仙市の「もるくす建築社」さん。
右に移っているのが、佐藤社長です。
写真が白トビしちゃっていますが、周りは雪・雪・雪。
軒下には屋根から落ちた雪が2?3mの小山になっています。

でも、玄関を一歩入ると、そこは春。
しかも、土間続きのワンルームで、大きな吹き抜けで二階と繋がっちゃってます。
厳冬地域でこんな間取りなんて、本当は有り得ません。
なのにっ!
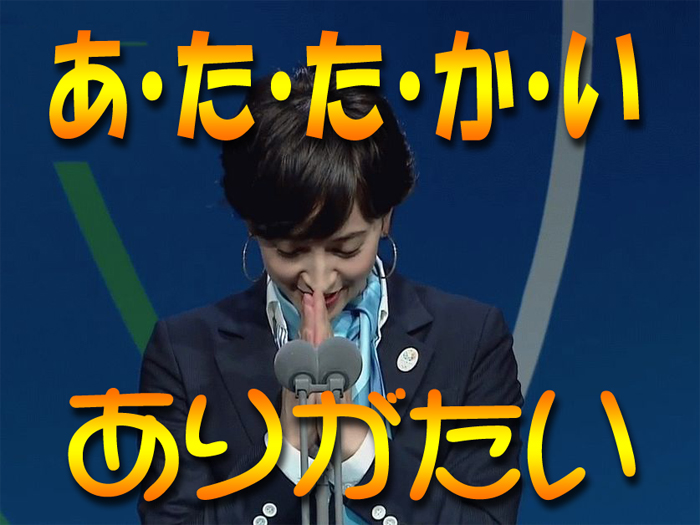
いや、私のギャグは寒いかも知れませんが、本当に、足もとから全ー部、暖かいのです。
床暖の足が熱い様な暖かさでもなく、
エアコンの頭がモワッとする暖かさでもなく、
お日様に干したての布団に入った時の幸せな暖かさ、とでも言いましょうか…。

暖房は、写真の薪ストーブがチョロチョロと燃えているだけ。
こんなに大きな開口部もあります。
住宅を断熱化しようとすると、ネックになるのは圧倒的に「窓」。
日本のサッシは諸外国に比べて性能が低すぎるのです。
(中国や韓国にも負けます)
ヨーロッパでは、すでにごく一般的なトリプルガラスも、日本では北海道限定販売。
ようやく春から本州でも販売が始まるようですが。
人が暑さ・寒さを感じるのは、気温だけではありません。
その人の、【周囲の床壁天井の表面温度】と、【気温】の平均を、人は温度として感じます。
だから、同じ室温でも、部屋の中心にいるのと、窓際にいるのとでは、寒さがまるで違う。
これは、体感的にお分かりいただけると思います。
床壁天井そして窓ガラスからも、熱線(電磁波)が輻射熱として出ているからです。
例えば、サッシメーカー大手、
リクシルの現在一番ハイグレードの樹脂サッシでも、熱貫流率(熱の伝わりやすさ)を見ると、
U=2.33
これは計算上、密度16kg/m3の、安ーいグラスウールの2cmほどの断熱性しか有りません。
いかに窓から熱が逃げるか分かりますよね。
で、こちらのお宅で壁の表面温度を測ってみます。
こんなの持ち歩いている私も変ですけど(笑)。

22℃。
室内の温度計は23℃。
ほとんど壁の表面温度と室内の空気温度が同じ。
だから、温度計の表示だけ見ると、寒そうな気がするけど、全然寒くないのですね。
で、驚くのは、このサッシのガラス表面温度。
まずは、参考までに、今朝のマクス。

温暖な富士市ですが、今朝は冷えた。
と言っても、測定時、外は4℃くらいかと。
薪ストーブ炊き始めていますが、室温はまだ16℃。
壁の表面温度は15℃。
これは断熱性が高いのではなく、単純に昨晩までの薪ストーブで建物が温まっているので、ほとんど差がない(16と15℃)だけでしょう。
窓は、現在は販売されていない、二重サッシ。
アルミサッシの建具が二重になっています。ガラスはシングルガラスです。
室内側のガラス表面温度が14℃。
室内側の窓を開けて、外側のガラス温度を測ると6℃。
薪ストーブで室温が上がってくると、ガラスと室温の差はどんどん開いてきます。
さて、戻って、東北のお宅のサッシ。
壁の表面温度が22℃でした。
外は氷点下ですが…

げっ!ここも22℃。壁の温度と同じ!
この放射温度計の精度とか原理によって、つまり測る素材によって、どの程度正確なのかは分かりませんが、それを差し引いてもこれはとんでもないことです。
このサッシのU値はなんと、0.79!
リクシルの一番良い樹脂サッシの、三倍以上の断熱性があります。
トリプルガラスの木製サッシ。
もちろん、値段は全然違います。
建築費と住宅の性能は、どこを落としどころとするか、これは非常に難しい問題ですが、静岡でここまですると、多分暖房費はゼロで行けるでしょう。
住人自体の体温と、照明と家電の熱、太陽からの取得熱、これだけで十分家を暖められるはずです。
こう言うのが本当のエコなんですね。
寒い家で、気合いと根性で暖房を使わずに過ごす、これもある意味立派な志だと思いますが、どう考えても、健康には害があります。
こちらのお宅のお施主様(二枚目の写真のおばあちゃん)、
「ほんと、この家の暖かさときたら…」
と、泣き出すんじゃないかというくらいの感激を込めて語るお話しが、心に染みました。
いやはや、かなり考えさせられました。
上には上があります。
まだまだ勉強です。
もるくすの佐藤社長、および東北の皆様、ありがとうございました。
温暖な静岡でどこまで出来るか…。
頑張るぞっ!
2014年02月06日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。