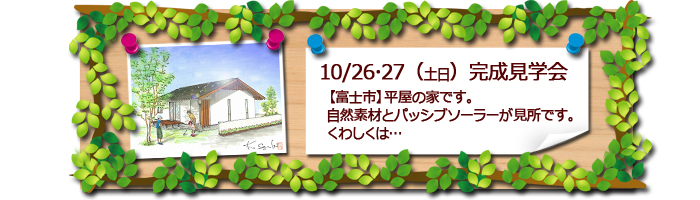土地の調査
本日は土地のお話しです。
新たに購入する際には、真っ当な不動産屋さんであれば、その土地に関する法的な情報はきちんと知らせてくれますので、まず問題ありません。
問題は、建て替えなどで、親や親戚の土地に家を建てる場合、その土地にどんな問題があるのか、そもそも建てることが出来るのか、これをしっかりと調べないと、後でとんでもないことになることがあります。
土地は法務局で「公図」や「登記簿」を取って調べます。
ですが、意外と知られていないのは、そもそもこの公図は、正確な土地の形を表すものではありません。
精度区分というのがありまして、古い土地では、この精度区分が低いものが一般的です。
その場合、土地の形・一辺の長さ・角度などなど、どれをとっても適当に作られたもの、くらいに考えた方が無難です。
平気で1mや2mはくるっています。
これは何故かと言えば、土地や河川などによって区切られた区画を、「こんな形に…」みたいないい加減な線を引いて筆を分けてしまったためです。

例えばこちら。
真ん中は公図では水路敷なのですが、水はありません。
公図だけを見ると、水路の巾は2m以上あります。
もちろん、水路の上に建物を建ててはいけません。
でも、はたして、水路の正しい位置は…?
さらに、よくあるのが、「かんち」。

うわっ、かわゆい…。あ、すみません、「カンチ」違いです。
正しくは「官地」です。
国の土地です。
この官地が、土地と土地の間に至る所にある場合があります。
どう見ても個人の土地に見えても、公図では官地、これ非常によくあります。
もちろん、官地も家は建てられません。
では、水路や官地の地図上の正しい位置は…?
実は、「そんなもの無い」と言っても過言ではありません。
正確に測量されている土地を除き、隣接する所有者(国や自治体や個人を含む)間で、「ここにしましょう」とするわけです。
もちろんその前提として古い測量図や地図などを調べたりもするのですが、基本はこれ。

複雑な場合は、こんな機械を用いて、

工務所の人に敷地の現況を調べてもらったうえで、
「公図と照らし合わせて、ここが敷地境界と考えるのが妥当だと思います」
として、建築確認申請を提出します。
建築確認申請は、あくまでその土地に、図面通りの家を建てて良いかどうかを判断するものですので、土地の境界を確定させるものではありません。
そして、公図の精度が悪くても、最低限、公図から読みとれる巾は官地として見ましょう、という暗黙のルールもあります。
なかなかやっかいなのです。

ただ、土地は境界の問題だけでなく、地盤の強度の問題もあります。
これは、この様に調べれば、スパッと明確に分かりますので、必須な工程ですね。
2013年10月08日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。