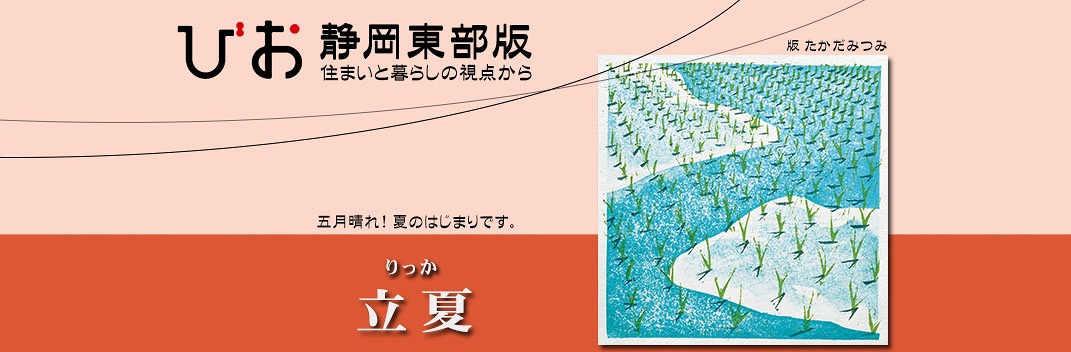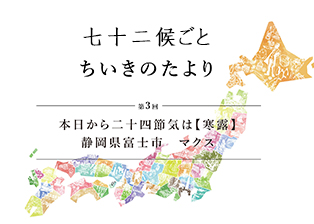自然災害伝承碑
こんにちは。設計の井出です。
本日より季節は、秋分の次候で【蟄虫坏戸:虫かくれて戸を塞ぐ】。
そろそろ寒くなってきて、外で活動していた巣籠もり虫たちが、再び土の中に潜って穴をふさぐことを示すそうです。
少しづつ、「ちょっと寒いかな…」という日も増えてきましたね。
唐突ですが…
今年の3月に、国土地理院が、新たな地図記号を制定したのをご存知でしょうか。
↓こちらが新しく増えたマーク。
皆さん、何を表すマークかわかりますか?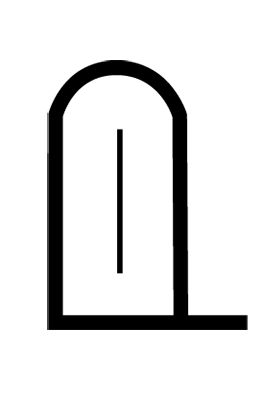
こちら「自然災害伝承碑」と呼ぶそうで、
過去に発生した津波、洪水、火山災害、土砂災害等の自然災害に係る事柄(災害の様相や被害の状況など)が記載されている石碑やモニュメントの場所を指すマークなのだそうです。
国土地理院のHPを見ると、石碑の場所を確認することができます。
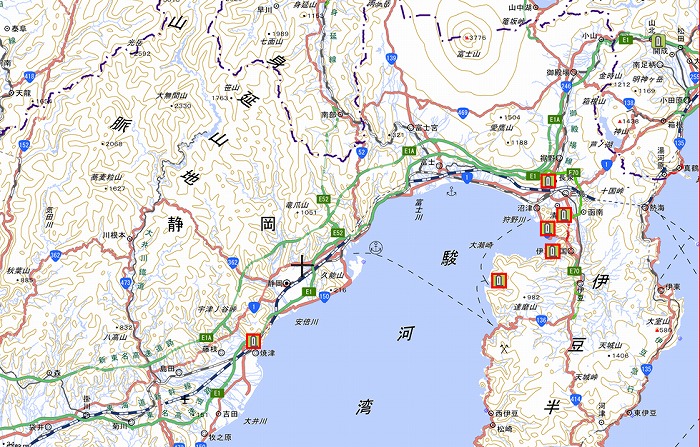
少々分かりづらいですが、赤い四角で囲っているところが、石碑の場所を示しています。
弊社の所在している静岡県では、計6箇所で確認することができました。
沼津、三島といった東部地区の沿岸部で多く石碑が建てられており、
災害内容の内訳は、
洪水が三件
土砂災害が二件
地震が一件
となっています。
今回はその内の一件、沼津市の大岡という地域にある石碑を見に行ってみました。
近くに小学校があり、その通学路の途中、住宅街の中にポツンとあります。

震災追弔の碑(しんさいついちょうのひ)。
1854年12月23日に起きた安政東海地震を追弔する石碑です。
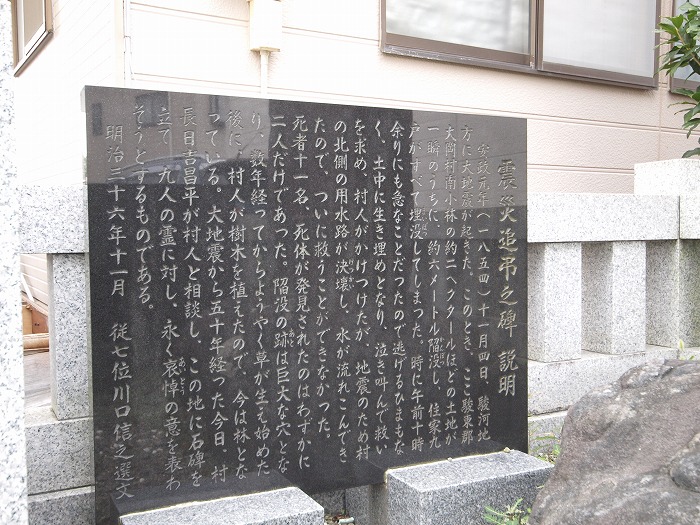
説明書きを読むと、このときの地震の影響により、駿河国大岡村(現沼津市大岡南小林)の約2ヘクタールほどの土地が一瞬のうちに約12~15m陥没して、住家12戸が埋没、9名が亡くなった、との記述があります。
1ヘクタールは10000㎡。100メートル×100メートルほどの大きさなので、
2ヘクタールがいかに大規模な陥没だったかが分かりますね。
このように、石碑には災害の被害状況などが刻まれており、これらの認知度を高めることで、地域住民の防災の意識を向上することが目的のようです。
近年は、地震だけでなく、異常気象の影響による台風や豪雨、洪水などの自然災害による被害も多く、ニュースでも度々報道されるようになりました。
いつ来るのかわからない自然災害、先人の教訓を活かして、日頃から万全の対策をし、災害に備えたいですね。
ちなみに、下記の記事では、「先人の教訓」とは対象的に、社長の鈴木が地震の「最先端のお話」を聞いてきた際の記事ですので、合わせてご覧くださいませ。
文:井出祭子
About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。
工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。
ビオブログアーカイブ
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (6)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (6)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (5)