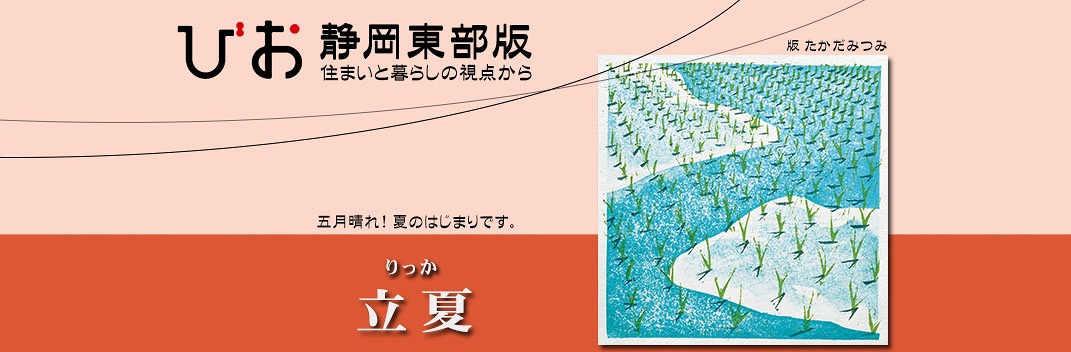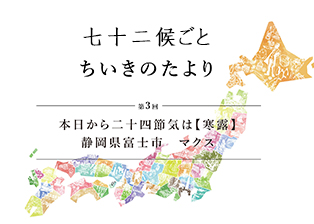おひまちさん
本日から二十四節気は霜降(そうこう)。
七十二候は、霜降の初候で【霜始降:しもはじめてふる】。
急に寒くなったと思ったら、富士山も白くなってますね。

霜降。
文字通り、霜が降り始める頃。
昔は霜は、雨や雪のように、空から降ってくるものだと考えられていたので、おりる、ではなく、ふる、なんですね。
そんな先日、町内会の行事で係だったため、「おひまちさん」に参加しました。

おひまちさん、ご存知ですか?
「日待ち」と書きます。
調べてみると、もともとは農村などで、田植えや稲刈りの終わった時期に、部落で集まって夜通し会食や余興をして夜明けを待つ行事だったようです。
私の町内にも小さな稲荷神社があり、稲を象徴する穀霊神である稲荷神を、前夜から潔斎して寝ずに日の出を待って、五穀豊穣と家内安全を祈念する、といったことが昔から行われていたのでしょう。

もっとも今は、役員とその年の当番さんが中心となって、浅間さん(浅間大社)の神主に祝詞を捧げてもらい、簡単な宴会をする、というものです。
今回私の家含め3軒が当番で、事前にお供え物の買い物や、注連縄の紙垂(しで)づくり、それから↑こんな飾りを作ります。
農家が減り、共働きが当たり前になったこのご時世、休みを合わせてこの様な飾りを作るのは大変ですが、昔は、青年部が集まり、町内全ての家庭に5本づつこれを作って配ったのだとか。
TVも大した娯楽も無い時代、こういった行事の準備は、一つの楽しみだったんでしょうね。

お稲荷さんは集会場に併設されており、敷地をぐるっと囲んで注連縄を張ります。
私達の作った紙垂も、長老方からクレームも入らず(笑)、無事取り付け完了。

女性陣は宴会の準備。
正直…
『忙しいのに仕事を休んでこんなこと、めんどくさ…』
『町内のオエライサンから文句言われても、キレないようにしなきゃ…』
『午後は仕事だからどうせ飲めないし…』
とか、
思わなかったと言えば嘘になりますが、
町内会長さんが、
「昔はもっと大勢集まって賑やかだったんだけどなぁ…」
となんだか寂しそうに言っていたのがとても印象的でした。
前々回、「菊花開」の時に「避難所生活を想像してみる」で書きましたが、大地震のときは、こういった地域の集会場が地域の要になります。
『いやぁ…ここで雑魚寝は無理だろぉ…』
と思ったのと同時に、この様な地域に昔からある行事が、全く無くなってしまっても、いざという時に助け合えないのだろうなぁ…、そう感じたのでした。
文:鈴木克彦
About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。
工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。
ビオブログアーカイブ
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (6)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (6)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (5)