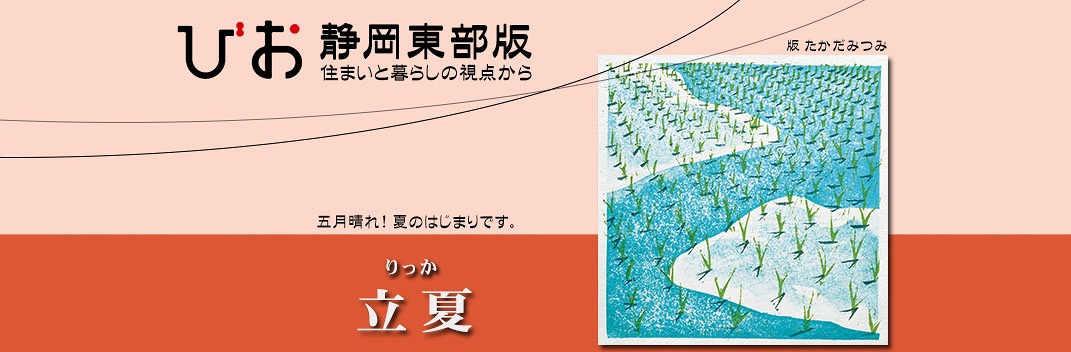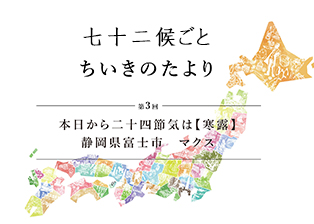官地って何だ?
季節は変わり、本日から二十四節気は【白露:はくろ】。
七十二候は、白露の初候で【草露白:くさのつゆしろし】。
たしかに、あれだけ暑かったですが、朝晩はずいぶん涼しくなり、冷え込みで、草木に朝露が着くようになるころですね。
さて本日のお題は、ちょっと難しいかもしれませんけど、土地のお話。
私達の住む富士市・富士宮市は、全国的にも「官地」が多い、ってご存知でしょうか?
『は?官地って何? 東京ラブストーリー?(古っ)』
官地の歴史的な経緯もふくめ、掘り下げてまいりましょう。
本日の社長ブログでは、地盤調査について書いているのですが、その調査した敷地を見ると、なんか変です。

上の写真で、青いテープは建物の配置を示すためにこちらで張ったのですが、左の一段高い敷地との間、見切りコンクリートが切れていますね。
な、なんで???

こういうことです。
黄色い部分、なにこれ?
じつは、ここが「官地」なんです。
そうすると、もう一つ疑問。
その「官地」とやら、自分の土地じゃないとすると、その官地と自分の土地との間に、境界を示す見切りコンクリートがありません。
分譲業者が忘れた? 予算下げるために手抜き?
いえいえ、違います。
それが、本日のお話。
ただ、最初にお断りしておきますが、こちらは法律の解説ページでも、歴史の解説ページでもなく、あくまで「読み物」として、一般の方向けにわかりやすく書いておりますので、細部の正確性については、あまり厳密に追求してないでいただきたいです。すみません。
と、最初に弱気におことわりした上で、そもそも官地とは何か?
明治のはじめ、政府は、従来の「米による年貢」から「お金による税金」に本格的にシフトするため、土地の測量を全国に命じます。
当時は、現在のように正確に測れる機械などありませんでしたから、その当時作られた公図は、割と適当だったりします。
そして、「土地の広さによって税金がかけられる」いわゆる固定資産税を考えた時、
自分が使っている田んぼなら、
「ん、ここは、おらの田んぼだ!」
と当然主張するわけですが、みんなも通るあぜ道とか、川沿いの法面とか、厳密に誰の土地でもないような部分については、自分の土地としてしまうと税金が高くなるので、
「いゃ、ここはおらんちじゃね」
となったわけですね。
すると、誰の土地でもないので、その部分を、お上の土地、としました。
これが、官地です。
ですから、現在の官地の所収者は「財務省」となります。
ちなみに、官地以外にも、公図を見ると誰の所有でもない謎の土地があり、
「赤道」と言ったり、「水路」と言ったりします。
水路はわかりやすいですね。
今、全く水が流れていなくても、昔は水路だったので、公図は青く塗られていました。
そして、昔は、道は赤く塗られていたため、現在明確に道路と分からないような、かつて道だった部分を「赤道」と呼んだりします。
赤道と水路は、基本的には市町村のもので、公共性が高いものですから、不法占拠し続けても、時効による取得は出来ませんが、財務省の官地には、この「取得時効」があります。
取得時効とは、民法で定義されていて、善意の場合(法律用語なので、善人悪人の善意ではなく、知らなかったの意味)10年、悪意の場合(同、知ってた、の意味)20年、公然と自分の土地として使っていると、自分のものにして良い、というものです。
もちろん、自動的にそうなるわけではなく、所得時効が成立しているから権利を主張できる、という意味です。
所得時効は、どの土地であっても民法でOKとされています。
ならば、、赤道も水路も、時効取得OKだろ?
というとそうではなく、
「公共性の高いものだからダメ!」
「どうしても、と言うなら裁判じゃ!」
となります。
だから、人の土地でも、当然そうなりますね。
ですが、官地は、時効取得が可能です。
財務省としては、(狭くて小さくて)使いみちがない土地を自分の土地にしておくより、民間に払い下げて固定資産税を取る方が、「得」ですからね。
けれど一般的に、官地は前述の通り、田んぼの畦道とかだったりした部分なので、小さく狭いので、誰かが使うとかではなく、隣接するその土地の所有者が、そのまま普通に使っていることが殆どで、第三者がそこを取りに来たりはしません。
だから、測量や登記など、わざわざお金を使って、払い下げたりせずに、(法律用語的には「悪意」で)そのまま使い続けます。
今回の土地も…
まぁ、周囲の状況から見て、上段の土地の所有者が、下段の方と揉めるの承知で使ったりなどしないはずなので、下段のそれぞれの土地の所有者が、なんとなく使い続ける、
でしょうね。
で、官地がどういったものか分かった上で、最後にもう一つ。
いつも一緒に仕事をしている土地家屋調査士によりますと、富士市・富士宮市は、全国的に見てもこの官地がものすごく多い土地なんだそうです。
なぜ?
って話なんですが、昔、天領(江戸幕府の直轄地)だったことによる、という説が強いそうです。
前述した土地の測量の際、「ここはもともと、誰の土地でもないお上の土地だから」ということで、そのまま官地になった場所がたくさんあるみたいですね。
家を建てる際に、よくこの官地が出てきます。
誰がどう見ても自分の土地に見えても、公図を見れば、自分の土地ではありませんので、当然その土地にはみ出して家を建てたり出来ませんし、建ぺい率や容積率に入れることは出来ません。
測量をして払い下げてもらう、とすれば、勿論どちらも可能です。
いかがでしょうか、官地、おわかりいただけましたでしょうか?
それにしても…
鈴木保奈美って、変わらず綺麗ですよねぇ…。
文:鈴木 克彦
About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。
工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。
ビオブログアーカイブ
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (6)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (6)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (5)