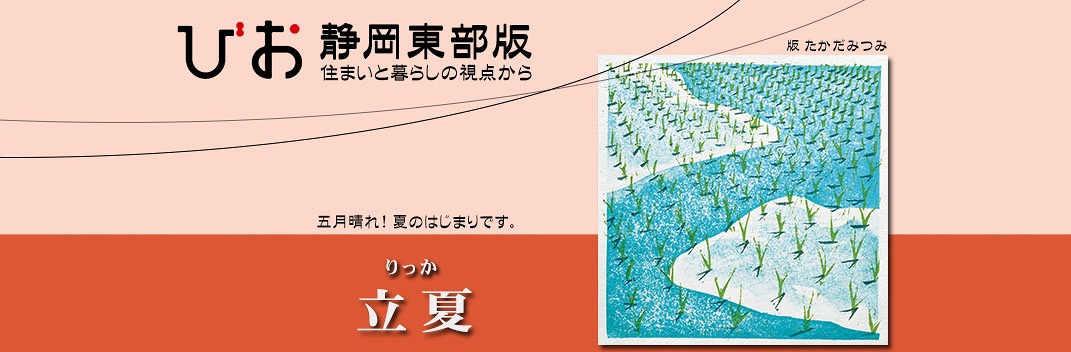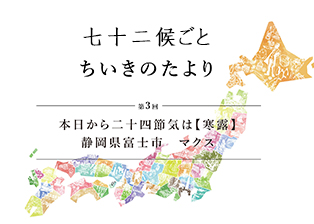狩野川の水の恵みとワサビ
本日より新しく始まりました『びお静岡東部版』というページでございます。
本日リニューアルの、住まいマガジン「びお」の、地方版でございます。
静岡県富士市の工務店、株式会社マクスから、家づくりの情報とは、また違った切り口で、
「住まいと暮らしの視点」から、ローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っております。
「旬」というのがポイント。
日本には、「二十四節気」という、季節の移ろいを表す歴があります。
現在はこれを旧暦と言いますが、一年を24に分けて、立春から始まり、大寒で終わります。
二十四節気は、一つの節気をさらに三分割した七十二候があります。
七十二候は、季節の移ろいを気象や動植物の成長・行動などに託して表しています。
365日÷72候=約5日
というわけで、この「びお静岡県東部版」は、七十二候を目安に、つまりほぼ5日毎に、様々な情報を、ゆるく(←ここポイント)発信してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、記念すべき第一回目のネタですが、現在は旧暦で、
二十四節気は、ご存知『秋分』。
そして七十二候は、蟄虫坏戸(虫かくれて戸を塞ぐ)です。
そろそろ寒くなってきて、外で活動していた巣籠もり虫たちが、再び土の中に潜って穴をふさぐことをいいます。
「戸を塞ぐ」というところが、趣がある表現ですね。
でも、人間は涼しくなってきたから、こもってる場合じゃない。
運動の秋です!
今回は、「自転車で出かけよう!」というネタで参りましょう。
先日、「狩野川ライド&ライド」という自転車イベントに参加してまいりました。
【狩野川源流大見の郷 水のめぐみを五感で楽しむ自転車旅】
という、ガイドさんがついた40kmの自転車ツアーです。

狩野川(かのがわ)は、静岡県東部・伊豆を流れる一級河川。
流域面積(川幅の合計ではなく、降った雨がその川に流れる土地の面積の合計)は、静岡県の一割以上を占めるそうです。
その狩野川源流の「水と食」を周るツアーです。
狩野川といえば、いや、静岡といえば、そう、ワサビ。
上の写真の左側は、ワサビ田。

わさび田の写真。
ワサビは葉が大きく、直射日光に弱いため、上の写真のように大きな木で木陰を作ったり、寒冷紗で日陰を作ってあげるんだそうです。

いきなりワサビ田から飛びますが、昼食に立ち寄ったのは、「中伊豆の時間」という古い民家を改装したお店です。

ワサビと並んで名産の椎茸を囲炉裏で焼いて出していただきました。
食べ物ネタをブログに載せるのは不慣れでして、美味しすぎて食べ終わってから写真を撮っていないことに気付く痛恨のミス…。

で、ワサビネタに戻ります。
ワサビには大きく、真妻(まずま)種と、達磨(だるま)種があり、味が良い小ぶりの真妻種は関東に、大きくて緑色も濃く、見栄えがする達磨種は関西に出荷されるのだそうです。
安曇野の畑ワサビも有名ですが、豊富な湧き水で作られる中伊豆の水ワサビは、日本一の品質を誇ります。
で、お昼に提供されたのが、上の真妻種、一人に一本!

ワサビは、下からすると苦味成分が出て美味しくないので、残っている葉の方の茎を取り、そちら側から優しく円を描くようにすります。
ご飯にカツオ節をたっぷりかけて、

ワサビ一本分をドバっと!
お醤油をかけて…。
ツーンとしますが、これが美味しいんです。
こんなにかけたら食べられないと思うかもしれませんが、生の本わさびは、爽やかな辛さとほのかな甘さがあり、意外と辛さが前面に来ないんです。
こんな美味しいワサビが出来るのも、狩野川源流の豊富な湧き水のおかげ。
狩野川は天城山に降った水が源流となりますが、「月に35日雨が降る」と言われる降水量日本一の屋久島が年間約4,500mmで、天城山も4,000mmを超える雨が降るのだそうです。

だからでしょう。このような、水を祀る神社もあります。

水神社の横のワサビ田。

湧き水。
写真だけじゃ伝わりませんね。
水中の様子を動画で見てみましょう!
可愛いメダカが泳いでいますよ。
(GoPROで撮影)
中伊豆では、ワサビだけではなく、椎茸の原木栽培や、静岡コシヒカリの生産も盛んです。

ただ、水に恵まれているとはいっても、平地ではないですから、高低差を解消して田んぼに水を引くのは大変です。
上の写真で、道路脇をガイドさんが説明してくれているのですが…

指差すところ。

岩山をくり抜いて、水路を作っています。
重機もない時代に、昔の人の血の滲むような努力があって、今の美味しいお米があるんですねぇ…。

こちらは別の水路。

先程の岩の穴は出口でしたが、こちらは入り口。

このような水路が昔から大切に守られてきています。

これは珍しい!
上の写真の水色に流れている川の下を、青色側に、下の写真の水路が直行しています。

この水路は後述しますが、発電用の水路です。
こちらのポイントで、またガイドさんからの解説。

狩野川は、昭和33年、狩野川台風で氾濫し、死者千名以上の大惨事を引き起こしています。
ガイドさんのお母さんの実家も写真奥にあり、流されたのだそう。
お母さんも命からがら脱出したのだそうですが、現地で見るかぎり、とても氾濫を引き起こすようなところには見えません。
災害って、そういうものなんでしょうね。

大きな災害の原因にもなった狩野川ですが、古くから命を育んできた川であることに変わりはありません。
上の写真は、先程の発電用の水路の水が流れるレンガ造りの水道橋です。
梅木発電所の水路橋で通称めがね橋。
今から100年以上前の明治44年完成で、総レンガ造りの当時の最新技術で作られています。
水路と言われてもピンとこないのは、水が見えないから。
水は、どこをどのように通っているの…?

どん。
上から見ると、こんな具合になっています。

滔々と流れる豊富な水。
ちょっと恐怖すら感じます。
これが100年前からすっと…と思うと、自然の力もすごいけど、人間の力も、またすごいですね!
今回自転車で回った伊豆国市は、地元ではありませんが、家内の実家にも近く、よく通っているところ。
でも、あらためてガイドさんの説明のもとゆっくり走ってみると、発見の連続でとても楽しい時間でした。
みなさんも、気持ちの良いこの季節、閉じこもって戸を塞いでいないで、外に出かけてみませんか?
文:鈴木克彦
About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。
工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。
ビオブログアーカイブ
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (6)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (6)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (5)