- 2010.02.17 水曜日
- 三島市の、次世代パッシブソーラーそよ風搭載の家(長期優良住宅)です。
一昨日のブログで、「ベランダや屋根の下なので断熱」と書きましたので、本日は昨日に引き続き、今度は「屋根」の部分をご紹介します。

こちらがその屋根の部分です。

防水をとった上に、まずはこの様な樹脂製の部材を取り付けます。

ちなみにこれは、瓦屋が瓦棒を腐らせないように使う部材です。

瓦葺きではないので「瓦棒」とは言いませんが、その要領で流れ方向に対し直行するように、下地木材を取り付けます。

この下地木材は、前もって、会社で篠原総務部長がたっぷりと防腐剤を塗って染み込ませてあるものです。
長さを切ると、その部分に防腐剤が塗られていなくなってしまうので、切った箇所にも防腐剤を塗れるように、現場にも防腐剤を置いてあります。
(一つ前の写真で足場の上の防腐剤の缶が置いてあるのが分かります)

この木を打ち付けてゆきますが、冒頭の部材のお陰で、木材が屋根の防水面から少しだけ浮きます(差し金が通っているのが分かります)。
どれくらい浮いているかを必死に城内監督が撮影中です。
この僅かな浮きが、万が一の屋根材からの漏水や結露の際にも、排水をスムーズにし、防腐剤を塗った下地木材の所で水が溜まらないので、下地を腐らせるリスクもぐっと減ります。
伝統の瓦葺きの理屈の応用です。

そして!
タイトルの通り、本物の木の屋根材を葺いて行きます。
言い出しっぺの責任を取り、ヘルメットをかぶって施工しているのは私です。
この木は、非常に腐りにくい、ウエスタンレッドシーダーです。
このブログでも、何度もご紹介しておりますが、マクスでは、ほぼ毎回外壁にワンポイントで使用している「木の外壁」と同じ素材です。

白く見えるのは、重なり部分にさらに防水紙を入れ、この材料自体を濡らさないようにするのと同時に下側の防水層へ水を回さないための工夫です。

やっぱり本物の木は違います。
「暖かさ」があります。
勿論、暖かいとか、キレイとか、そんな抽象的な理由だけで住宅の材料に用いることはあってはならず、特に外部は「燃えない安心」が必要になります。
普段外壁に使っている材料と同様、この屋根材も「燃えない」加工がしてあります(外壁の燃えない加工についての以前の記事)。

先日、雨の日に撮影しました。
濡れるとレッドシーダーの赤が、何とも言えず美しい…。
あ、でもこの上に耐久性を高めるために、後で塗装しますけど。
いつかは張りたいなぁ〜と思っていましたが、張らせていただけるお客様に巡り会えたことに感謝ですね。
【補足】
営業マンに強く依頼されていますので、メーカーサイトをご紹介します。
CHANNEL ORIGINAL WILLROOF

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - 桧の家 住宅のお話し > 【三島市】パッシブソーラー | comments (2) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
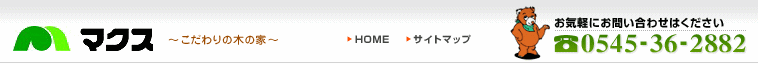

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 木の屋根!?
マクス社長の住宅Blog
木の屋根!?
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
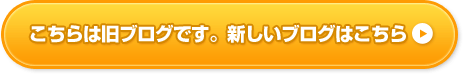

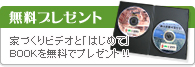


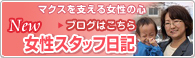




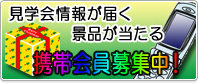

Comments
この屋根、これから富士にも沼津にも裾野にも出現させます。
木の家を、ゲリラ的にでもポツポツと出現させていけば、いつか町並みも変わってくる…
と良いなと思います(笑)。
ウィスラーの屋根本当にいい感じですね。三島もGoodです。