- 2009.06.22 月曜日
- 6/10日のブログで、犬山の如庵を見学したことを少し書きましたが、その時のブログの内容があまりに薄かったので、茶室について加筆です。
と言いましても私、茶道など全く分かりませんので、あくまでも建築としての空間に感じたことなどを書かせていただこうと思います。
先日、沼津方面の仕事の合間に沼津市の御用邸記念公園に行って来ました。
もともと御用邸は、大正天皇(当時皇太子)のご静養のために造営されました。
御用邸は沼津市の西伊豆の入口にあります。
余談ですが、その昔、国道414号線の御用邸までの道路(幅が八間あることから、地元では、はっけん道路と呼ばれます)は、天皇陛下が通る道ということで、一段高く作られており、後にそれに合わせて皆が盛り土をした(だから現在は高くない)ため、八間道路の近くで工事をすると、予想外の場所で変な土が出たりします。
この御用邸は、明治26年に完成し、その後増築されて、延べ床1,500坪の壮大な和風建築物となったのですが、戦争で消失しました。
現在、この焼失した本館の別館の、西付属邸と、東付属邸があり、この二つの建物がだいぶ離れていることからも、焼失した本館の大きさが想像されます。
戦時においてもこういった施設は標的にしないのが暗黙のルールだと思うのですが…。
それはさておき、
その東付属邸に翠松亭と呼ばれる茶室があり、その翠松亭に付属する形で、千利休の作とされる国宝待庵の写し「駿河待庵」があります。
直木賞を受賞した山本兼一著『利休にたずねよ』で、ちょっとした利休ブーム。
タイムリーなことに、昨日の大河『天地人』でも利休の回でしたね。
さて、この駿河待庵ですが、本物の写し、といっても、かなり立派な物です。
先日山崎に行った際に見学した、山崎歴史郷土館のレプリカは、実物大とは言え、模型的要素が強く、迫力に欠けますが、この駿河待庵は一見の価値アリです。
築年数は39年。
私が生まれた歳に出来た!
そんなことでも妙に唸ってしまいます。



上の写真で、側面の上の方に小さな明かり取りがあります。
待庵の窓は、壁を刳り貫いて出来ている、というか、壁の一部を壁にせずに窓にした、というか…。

↑この写真だとお分かりいただけるでしょうか?
最近ではほとんど見なくなりましたが、木舞壁といいまして、竹で編んだ下地に藁を混ぜた土を塗ったのが昔の壁です。
その土を塗る際に、窓にする部分は土を塗らなかった、というわけです。
『利休にたずねよ』を読むと、この窓を作る際、そして茶室の入り口:躙り口(にじりぐち)を作る際に、利休がどう考え、どう職人に指示したか、なども垣間見えて面白いです。
ちなみに、犬山にある本物の国宝の待庵は、一ヶ月前から見学予約が必要で、私は見たことがないのですが、本物は上の写真にあるこの側面の小さな窓二ヶ所のうち、一ヶ所が傷みが酷く、修復が出来ないということで塞いでしまったらしく(解説ボランティアのおば様談)、利休(とされる)の考えた通りに出来ているのは、本物の国宝よりもより近い、のだそうです。
たかが小さな窓、と言っても、この茶室の最大のポイントは、狭さと光。
『利休にたずねよ』ばかりで恐縮ですが、本の中で、石田三成が、
侘び茶は利休が始めたわけではない。
あの男は、まるで自分が茶の湯のすべてを創始したような顔をしているが、
そもそもいったいなにを新しくあみ出したというのだ。
あの男、茶の座敷を狭く暗くしおった。
なぜそんな狭い座敷をつくるのか、まこと理解に苦しむ。
と考えるシーンがあります。
そう、他の茶室に比べて、ひどく暗いのです。

窓からレンズだけを入れて、フラッシュをたかずに、シャッタースピードを遅くして、広角レンズで撮りました。
なので、目で見た感じよりはっきり写っていますが、実際に、晴れた日に、にじり口からこの茶室に入れば、目が慣れるまで多分細部がよく見えない程暗いです。
何故そんなに暗くしたのか…?
その辺は、本をお読み下さい(笑)。
その意味で、計算され尽くした暗さ、光と陰は、先程の窓の関係で、本物より本物に近い、となろうと思います。
そしてもうひとつ。
狭い。
そう、確かに狭いのです。
客と向かい合うスペースは、床の間を除いて二畳、つまり一坪です。
今の住宅なら気の利いたトイレくらいです。
そして、天井も低い。
高さは六尺、つまり1.8m。
背の高い人なら頭がつきます。
一部を勾配天井にして変化を付けていますが、それにしても低い天井です。

室内だけを特別に低く作っているわけではなく、外も低いです。
上の写真の下家の屋根を受ける丸い梁は、下側で背の低い私(身の丈五尺四寸五分:165cm)でもすれすれです。
真っ直ぐ歩くと髪の毛が触ります。
小説は別にして、何故ここまで狭く、低く、暗くしたのか…?
茶の湯の侘び寂びを理解しない私、正直、考えても分かりません。
小説の中では、躙り口から中に入った利休の妻宗恩が、
「牢屋みたい」
と言っていますが、たしかにここに一日幽閉されたら壁をぶち破って外に出たくなるかも知れません。
が、しかし!
立ち入り禁止なのは勿論ですが、そういった衝動が起こるのかどうかを確かめるのも含め、無性に入ってみたいと思わせる『妖気』にも似た雰囲気がある、と言いましょうか、そんな空間です。
そして確かに美しい…。
実は、先週島根県に出張に行って来ました。
そのご報告はまた別の回にも書かせていただきますが、松江市で、
鳥取県指定文化財の『明々庵』を見てきました。

明々庵は、茶人として知られる松江藩七代藩主松平治郷(号を不昧)によって、待庵より約200年後に建てられた席で、茅葺きの厚い入母屋の屋根が特徴です。
余談ですが、待庵の屋根は柿葺き(こけらぶき)。
木の板の屋根です。
何故木の板が柿なのか?
実は、もともと木偏に市の柿ではなく、「朮」の点の無い字だったようです。
脱線終わり


今回もカメラのレンズを押し込んで撮影。
待庵が二畳+次の間の三畳であるのに対し、明々庵は、炉辺も入れて三畳なので、随分広く見えますが、建物自体の大きさはほぼ同じ。
でも、待庵に比べて随分開放的に見えるのは、天井が高く明るいからでしょう。
但し、高いといっても見立てで2mほどです。
如庵の事を書いた際に、織田信長の実弟の庵主織田有楽斎は、千利休の待庵を「人を苦しめる」と酷評した、と書きました。
待庵と如庵、二つの国宝でもこれだけ意見が分かれるのですから、私にどちらが正しいなどと言えるはずもありませんし、これら茶室に関しては、検索すれば、もっともっと本格的な考察を記したサイトは沢山見つかります。
興味がある方は、そちらを見ていただきたいのですが、これら茶室の見学を通し、広さと狭さ、明るさと暗さ、その難しさと面白さを改めて強く感じました。
この広さと明るさの考察については、もう何回か書かせて頂こうと思っておりますので、忍耐力があって、さらに心優しき方は、私の駄文にお付き合い下さいませ。

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - ミニ建物探訪 | comments (5) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
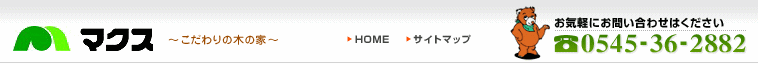

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 利休さんに教えてもらおう
マクス社長の住宅Blog
利休さんに教えてもらおう
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
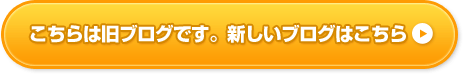

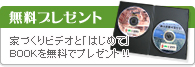


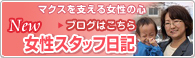




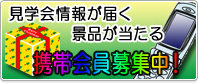

Comments
茶室は深すぎてその真意を理解するには、私には人生経験が少なすぎます。
全く意味を理解出来ない茶室の建築として…
(「武家屋敷でも小さな部屋に…」の記事に続きます)
富士の大将へ
待ってました。
待庵と明々庵のご案内ありがとうございます。
待庵の二畳台目は狭いですよね。
その暗い渋さ故か、利休鼠や利休茶、藍利休、
信楽利休とか、渋い色に利休が冠されてますね。
料理でも使われているのですね。
「あ〜めがふるふる城ヶ島の磯に♪
利休鼠の雨がふる♪}
お薄茶でもいただこうかな。
そうそう、渋い灰色は利休鼠と言いますね。
本を読むまで知りませんでhしたが、千利休って料理も一流だったんですね。
というか、茶の湯は、まず旨い料理があって、その後にゆっくりと茶を味わう席のことさえ知らなかった私…(恥)。
千利休と言えば、日本料理では、胡麻を使った料理には、“利休”とつけます。
ブームのついでに・・・。