- 2008.11.18 火曜日
- 現場監督ブログで、富士市の某神社の鳥居の工事風景が紹介されていますが、鳥居の入れ替えにあたり、前回設置した鳥居もマクスで施工させて頂いたものですので、その考察を少々。
前回の鳥居も、今回の鳥居も桧で製作致しました。
鳥居も含め、ウッドデッキなど特に外部で使用する木材は、何回かご紹介させて頂いた通り、腐りにくい樹種を選択するのはもちろん、腐らないような工夫・配慮が必要です。
前回も、薬剤注入や柱の根本に銅板を巻くなどの方法をご提案させて頂きましたが、当然予算の問題もあるのと、
「こういうものは5年毎くらいで立て直すべきだ」
との意見も氏子の方々から上がり、防腐や白蟻に関する特別な処置無しでの施工となりました。
8年ほど前のお話しです。
そうは言っても、折角ご依頼頂いたので、独身で暇だった私は、休日にプロパンガスバーナーで土中に埋まる部分を焼いたり、防腐剤を塗布したりしました。
何もしないよりは多少は良いだろうと思いまして。
で、その結果はこちらです。

廃材用のコンテナに捨てられた鳥居の根本(土に埋まっていた部分)です。
腐りももちろんありますが、白蟻さんにかなり食べられています。
今回は、薬剤注入をする予算も付いたので、かなり長持ちするのではと期待しております。
10年後にどうなったかご紹介しますので、10年後のブログをお楽しみに!
さて、上記の写真で、さらに寄ってみますと…

面白い形に白蟻に食べられていませんか?
中心部を残し、外側だけ食べています。
これは、外側から食べていって、ここまで食べ進んだ、と言うわけではありません。
白蟻の食欲は恐ろしく、その気になれば一ヶ月もあればこれくらいのボリュームを食べ尽くす事が出来ますので。
なのに何故この様になっているかと申しますと、
木には、中心部分の『赤み』と、その周辺の『白太(しらた)』の部分があるためです。
木が成長をしているのは白太の部分で、赤みの部分はすでに成長を終えた部分です。
木は外側に外側に、新しい年輪を形成して行きますので、成長が終わった部分から、白太が赤みへと変わります。
この際にデンプンなどの糖類やタンパク質等の栄養素(腐朽菌や白蟻にとっても栄養素)から、テルペン・フェノール・タンニン・ワックス類等の抽出成分にとってかわります。
これらは、腐りにくい成分であり、その成分の種類や量は、木の色や香りと言った樹種毎の特徴の違いとなります。
つまり、
高齢の樹齢の木の方が、赤身が多く、耐久性がある部分が多い
ということですね。
【蛇足】
白蟻も人間も、美味しいものはよく食べる。
パスタ作りが「何か」のヒントをくれたのか、休日の蕎麦は、コシ・のどごし共、最高傑作でした。

(見た目はまだイマイチですが、味はちょっとしたお店レベルじゃん…と自己満足)

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - 桧の家 住宅のお話し | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
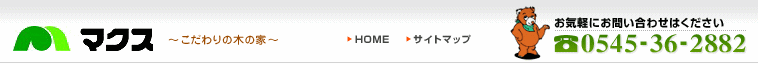

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 白蟻は白太がお好き
マクス社長の住宅Blog
白蟻は白太がお好き
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
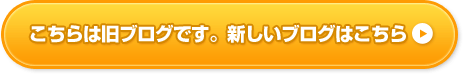

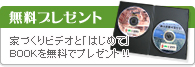


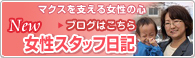




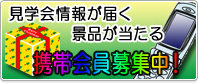

Comments