- 2008.01.24 木曜日
- 東京から帰って参りました。
今回は照明に関する講義を聴きに行ってきました。
私は、普段から、照明計画を考える際に、部屋の広さに応じて、部屋の真ん中に照明器具を取り付けて、
「はぃ、OK」
と言う様にするのではなく、出来るだけ間接照明で、「良い雰囲気」を出すことを心がけておりまして、それを、もっともっと上手くなりたい、と今回お勉強に行ってきました。
秋葉原のショールームも見てきたのですが、照明器具だけでなく、「本物」と呼ばれる家具や設備器具の数々の展示は、非常に目の保養になりました。
一千万のキッチンセットも見てきました(笑)。
なので、色んな意味で勉強になりました。
次回のご提案の時から早速活かして行こうと思います。
でも、今回一番勉強になった、と言うか考えさせられたのは、現在問題になっている二酸化炭素を減らすと言うことですね。
オーストラリアでは、白熱電球が禁止され、蛍光灯に切り替え、というのが、国をあげて行われているそうです。
日本でも、マクスでも取り組んでいる、「チームマイナス6」の一環で、電球を蛍光灯に切り替えよう、と言うのを政府も言っています。
安部さんが電球型蛍光灯をもっているCMやポスターを大量に製作したのが、突然の辞任で無駄になったとか…(余談ですが)
でも、日本は既に、家庭での照明の8割が蛍光灯だそうです。
で、こっからちょっと難しくなります。
(そして、講師の河原武儀先生の受け売りです)
・6畳の部屋を考えます。
・平均照度を100ルクスにすると仮定します。
・すると、白熱灯では180W(ワット)、蛍光灯では60Wが必要です。
・上記の消費電力は、白熱灯が180W、蛍光灯が72Wとなります。
・これを、一日5時間点灯させた場合の電気代を考えます。
・電気料金が30円 / 1KWh の場合、白熱灯が27円、蛍光灯が11円となります。
・蛍光灯の方が安いですね。
・ところが、「快適さ」という観点から考えるとももっと複雑になります。
・白熱灯では、最初の設定の100ルクスで十分快適に生活できます。
・ところが、蛍光灯では300ルクス無いと快適に感じられません。
これは、クリュウソグラフというグラフで実証されています。
・すると、実際には、蛍光灯ではこの三倍のW数が必要となります。
つまり、216Wになります。
・電気代も、11×3で、33円となり、白熱灯の27円より、むしろ高くなります。
白熱灯は、蛍光灯に比べて、熱を出しますので、冷暖房まで考え出すと、もっと複雑になるのでしょうが、「快適性」を考慮すると、決して蛍光灯の方が電気代が安いとは言えない、と言うことでした。
なるほどと思いましたね。
それと、蛍光灯型ランプに、電気代何分の一、ってよく書いてありますけど、消費電力はそうかも知れませんが、電気には基本料金、というのがあって、基本料金は。電球の種類によらず一緒ですから、電気代自体が何分の一、というのは、上記の様な面から考えると、ちょっと首をかしげたくなりました。
やはり、昔の人が言って来た様に、
「もったいないから使わない電気は消しなさいっ!」
これが核心なのでしょうね。
で話は変わりますが、こっからは講義の受け売りではなく、私が感じたこと。
コンビニ(ミニストップ)でおそばを買ったのですが、「有料の割り箸」と言うのがありました。

一本というか、一膳五円です。
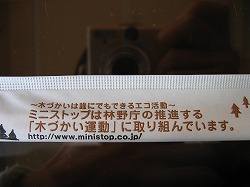
ミニストップの「木づかい運動」というものだそうです。
そもそも、割り箸は、日本の文化だと思います。
古くから、間伐材で箸を作っていました。
ところが、大量消費・コスト削減から、現在では、ほぼ全てと言っていいほどが、安い中国産です。
間伐材ではないので、森林を破壊し、割り箸を作り、禁止されている薬剤処理をし…、
と言う問題定義をしているニュースの特集を見た方も多いのではないでしょうか?
森を片っ端から破壊してしまっては、地球が破滅します。
しかし、森は育てなければならないという側面もあります。
枝打ちや下草刈りをすることで、木の生長が早まります。
材木適サイズ(樹齢30〜60年)を過ぎて大きくなった木は、二酸化炭素の固定能力も下がります。
建材としての材木でも、育てる課程で出た間伐材の割り箸でも、価格で外材に押された国産材は、放置され続け、森は荒れています。
森と林業の国、日本では、やはり森を守って行かなければならない、
そう感じます。
使うことで森は守られ、二酸化炭素も減るのです。
もちろん、目の極度に詰んだ、カナダのレッドシーダーも使うのですが、それは用途に応じてです。
森林資源・それがもたらす漁業資源・二酸化炭素・地球環境、そんな面からも、森を見直さなければいけない、と感じました。
でさらに、帰りの山手線の車内広告で見つけました。
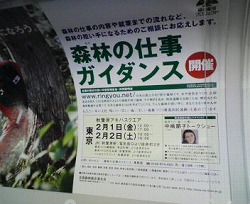
森の仕事ガイダンス
林業が魅力溢れる仕事に戻って欲しいですね。 - 日記・育児 | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
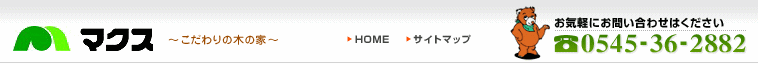

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 二酸化炭素を減らす
マクス社長の住宅Blog
二酸化炭素を減らす
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
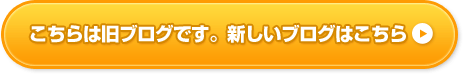

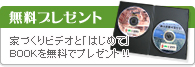


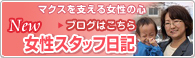




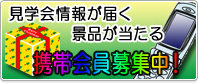

Comments