- 2010.08.05 木曜日
- 昨日の続きです。
さて、水につけておいた乾燥剤がどうなったかと言いますと、

水が乾燥してひからびていますが、こんな具合に固まりました。

最初の砂粒状から大分変わりましたね。
そう、タイトルからもうお察しの通り、これが漆喰の正体そのものです。
乾燥剤である石灰は、生石灰(“きせっかい”又は“せいせっかい”)と呼ばれ、科学用語で言えば、酸化カルシウムです。
簡単に言ってしまえば、酸化カルシウムは、石灰岩を焼いて作ります。
石灰岩は炭酸カルシウム。
これを焼く、つまり酸化させて、酸化カルシウム(生石灰)となります。
昨日の実験の様に、酸化カルシウム(生石灰)は、水と反応すると、水酸化カルシウムとなります。
水酸化カルシウムは消石灰であり、グラウンドに引くラインや、今年大騒ぎされた口蹄疫での消毒に使われたものが、この水酸化カルシウム(消石灰)です。
ちなみに、消石灰はアルカリ性が強く、皮膚もただれます。
目に入ると失明の恐れもあるので、グラウンドのラインは、現在はより安全な炭酸カルシウムの使用が推奨されているそうです。
以前、天井を漆喰塗りしている際に、左官職人の目に入って大騒ぎしたことがあります(もの凄く痛いそうです)。
だから、

こういうことをやった後は激しく手(この場合足も)を洗いましょう(笑)。
水酸化カルシウムは、空気中の二酸化炭素と反応し、炭酸カルシウムになります。
これは、冒頭の、炭酸カルシウムが酸化カルシウムになった酸化反応の逆で、還元反応です。
つまり、
石灰岩(炭酸カルシウム)CaCO3:貝殻や大理石もこれが主成分
↓
生石灰(酸化カルシウム)CaO:カップ酒やお弁当を暖めるのも実はこれ
↓
消石灰(水酸化カルシウム)Ca(OH)2:漆喰
↓
石灰石(炭酸カルシウム)
と、一周するわけですね。
壁に塗るときの漆喰の正体は、水酸化カルシウムです。
日本の昔ながらの漆喰は、海草の抽出物と練って作られます。
漆喰を作るには、大量の水の中で、生石灰を寝かせて水と反応させて作ります。
壁に塗られた漆喰は、上記の通り、空気中の二酸化炭素と反応して、ゆっくりと炭酸カルシウムになって行きます。
つまり、徐々に固まって、一枚の薄い石灰岩になるイメージですね。
だから長持ちするのです。
でも、何事もそうですが、長所と短所があります。
それはまた明日に続きます。
リレーフォーライフ チームメンバー&募金募集中です

- 桧の家 住宅のお話し | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
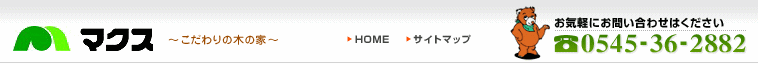

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 漆喰の正体 中編
マクス社長の住宅Blog
漆喰の正体 中編
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
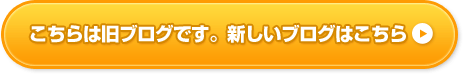

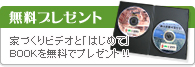


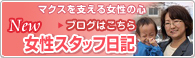




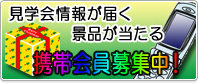

Comments