- 2010.05.28 金曜日
- 昨日は、車内よりノートパソコンで上棟作業をアップさせていただきました。
便利なような、機械に働かされているような…。
愚痴はさておき、車の中なのであまり詳しく書けなかった、冨嶽町家の命とも言うべき、
『平角スケルトンシステム』を中心に、二日間の上棟作業の様子を振り返ってみましょう。
『平角スケルトンシステム』は、建築家の趙海光先生が考案した、頑丈な躯体を作る考え方です。

上の写真で大工が施工している部分は、通し柱の二階床部分です。
4寸×8寸の平角、つまり通常は太い梁として使う材が、通し柱になっており、その平角の通し柱に、同じく4寸×8寸の平角の梁(二階の床梁:胴差)を組んでいるところです。

今度は、直行するもう一本の床梁を同じく先ほどの通し柱に組んでいます。
梁が刺さる部分の加工部分(仕口)が、通し柱が平角であるが故に、位置がずれている(離れている)のが良くお分かりいただけると思います。
つまり、その分、通し柱に加工されずに残った肉の部分がまだたくさんある、
と言うことになります。
これを、断面欠損が少ない、と言います。

この様に、6m四方の四隅の通し柱を平角にし、その間を同じく太い梁・桁で、しかも、継ぎ手のない一本の6mの長尺材でつなぐ、というのがこの平角スケルトンシステムのミソです。
分かりやすいように、6m四方の空間(ここをまさに『ベース』と呼びます)に、色つけしてみると、

こんな感じです。
この空間を、がっちりと固めて作るのが基本になります。
通し柱と梁・桁が、全て4寸×8寸の平角の、6mの長尺材を使っていますが、これはどこでもある材ではありません。
山側と協力し、この良質な材をストックしてもらう、川下の我々工務店も、部材をルールに則って、出来るだけ統一する、この協力関係で、良材の国産材をしっかりと使って行こう、という深い意味もあります。
話がそれ始めそうな雰囲気になってきましたので、元に戻して、

こちらは、その通し柱の頂上部分。
4寸×8寸の梁が乗り、

この梁と、

もう一つの梁も、平角だから、二本とも通し柱の上に、安定して乗っています。
同時に、この二本の梁と梁は、『茶臼』という仕口で組み合わさっています。
言うまでもなく、


これらシステムの性能を担保するのは、このシステムと同時に、目の詰んだ高樹齢の材を、含水率・ヤング係数の全数検査によって合格したもののみが出荷されるという、厳格にグレーディングされた材料を用いることにもよっているのです。
こういった事の積み重ねが、「先導的」と認められるので、国から200万円の補助金を受けることが出来る、
と言うわけですね。
なお、昨日の打ち合わせで、お客様のご厚意により、構造見学会を開催出来ることとなりました。
この国から200万円の補助金が出る「長期優良住宅先導事業認定」の冨嶽町家のしっかりとした構造を、是非ご見学下さい。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
【冨嶽町家 構造見学会】22年6月19(土)・20(日) 富士市厚原

- 冨嶽町家 > 【富士市】パッシブソーラー | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
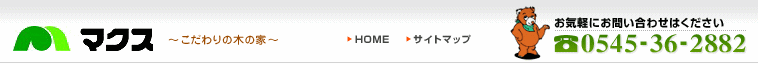

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 平角スケルトンシステム
マクス社長の住宅Blog
平角スケルトンシステム
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
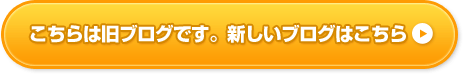

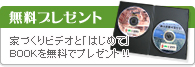


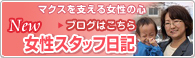




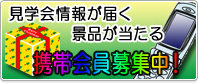

Comments