- 2007.08.27 月曜日
- 静岡県三島市のティンバーフレームの現場です。
先週に引き続き床暖のお話です。
今日は総務部長の篠原と一緒に床暖の施工職人と化してきました。
会社をほっぱらかして二人で脱走のつもりでしたが、この暑さ、まさに修行でした。
床暖の上は化粧フロアーではなく、無垢の栗の木を張ります。
合板の上に1ミリ程度の薄くスライスした板を張った化粧フロアーの方が床暖との相性が良いのですが(熱による収縮による狂いが少ない)、やっぱり無垢の方が好きです。
多少季節によって床鳴りがするかも知れませんが、それはお客様にご説明して、やっぱり木が良い、と分かってもらった上で使っています。
さて、そのとき注意しなければいけないのが床下の湿気。
床下から湿気が上がらないように、この様に気密フィルムを張ります。

私は基本的にはあまり高断熱高気密、と言う物に魅力を感じません。
ちょっと前、この言葉に、これからの建築は高断熱高気密だ、とかぶれた時もあり、関係資格を取ったり、本を読みあさったり、自宅も高断熱高気密にしましたが、ちょっと違うんですよね。
高断熱高気密信者が最終的に言うのは、エアコンを24時間365日つけっぱなしにして計画換気にして、それでも電気代が安くなって一年中快適で…
てな感じなんですが、日本には四季があって、春と秋は窓を開けっ放しにして自然の風を感じたいし、エアコンの冷房も暖房も肌に合わない人が多い。
薪ストーブに魅力を感じる人もいれば、風鈴とうちわで夏を感じる人だっているはず。
今は一番大事な事は、永く安心して暮らせる事。
つまり、頑丈で耐久性の高い構造駆体と自然素材で造る家です。
ただ、気密自体は無意味とは決して思ってはいません。
元々の高断熱高気密というのは、
住宅の快適性を求めて断熱材を厚くした結果、
↓
室内外の温度差が大きくなり、
↓
室内の湿った暖かい空気が乾いた冷たい外気へと漏れて流れ出る際に、結露して黴びたり腐りの原因となる
↓
だから、室内の暖かい空気を換気扇からしか外に出さないようにする
と言う事だと私は理解しています。
だから必要なところにはちゃんとシートを張るし、隙間風が入りそうな部分にはさらにこの様に羊毛断熱材を詰め込んだりするわけです。


とにかく理詰めで数字でまくし立てるんじゃなく、必要な事をやった上でもっとこだわるところは別にある、とそんな風に思うわけです。
って、今日のブログはやや理屈っぽいですね。 反省。

今日はここまで、また明日頑張ります。 - ティンバーフレーム 建築現場より | comments (2) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
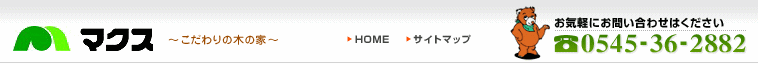

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 床暖の施工
マクス社長の住宅Blog
床暖の施工
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
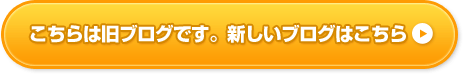

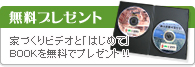


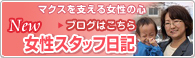




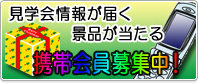

Comments