- 2010.01.15 金曜日
- 本日もティンバーフレーム工法の家の上棟風景をご紹介させていただきます。
本日ご紹介するのは、昨日の続きというか、前段階というか、お施主様へのご報告を兼ねて、ちょっと番外編です。
昨日の下家の柱、
「風を受けた際に心配…」
とのことでして、
「後からより強固な接合方法をとるのは難しいですねぇ…」
何て話をしていると、最近の施主様は凄いですね、インターネットで私達の知らないのをバンバン探して来られます。
その取付をご紹介。

独立基礎に正確に墨出しをし、
会社にある、一番長い振動ドリルで穴を空け(約30cm強)、

ケミカルアンカー(薬品の化学反応で固定)を二本入れ、

16ミリのボルトを叩き込みました。
もちろん、コンクリート打設時に埋め込むアンカーの方が強度は出ますが、打ち込む力加減からの感想では、この接合でも、かなりの引き抜きに耐える力は期待出来そうです。

専用ナットで繋ぎ、

桧の柱に横穴を開け、

同柱の根本に、先程の連結ナット用のを穴開け、

ボルト用の穴を開け…、
と、これが桧の年輪の固い所で刃が曲がって進んでしまうため、難しい〜の、何のって…。

何とか穴を空け、手探りで金物通しを連結し(柱の内部での作業なのでこれまた難しい)、引き寄せ、つまり引っ張ります。
横穴から専用のビットを差し込んで回すと、ボルトを引っ張るという凄い機能がこの金物には付いています。

大工も驚く程がっちり留まりました。
柱の表面にはこの黒丸が見えるだけです。
よく考えたもんだと感心しました。
ちなみに、木が黒っぽく汚れているように見えるのは、掘った部分に、金物の施工前にたっぷり防腐剤を染み込ませたためです。
後程の塗装工程で見えなくなります。

この金物は本当は専用の機械で施工用の穴を掘るので、現場加工には向かないなと言うのが正直な感想です。
三本施工するのに、ほぼ一日がかりでした(慣れたから次はもっと早そうだけど)。
商品も工法も日々進化します。
まだまだ・もっともっとお勉強しないと大変です。
1/23(土)ティンバーフレーム工法の家:構造見学会のお知らせ

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - ティンバーフレーム 建築現場より > 【富士市】パッシブソーラー | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
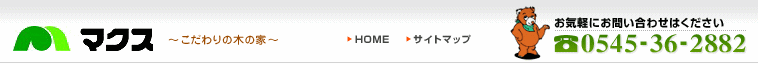

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > ティンバーフレーム上棟風景4|富士市
マクス社長の住宅Blog
ティンバーフレーム上棟風景4|富士市
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
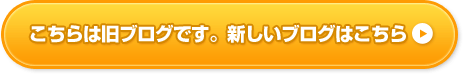

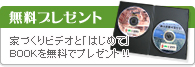


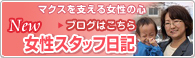




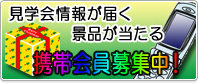

Comments