- 2009.01.15 木曜日
- 一昨日、薪ストーブでピザを作ったお話しを書きましたが、本日はその続きのようなお話しです。
薪ストーブで一番のネックはやはり燃料の薪です。
富士市や富士宮市では、長野のように薪ストーブが広く一般に普及している所と違い、薪が手に入りにくいと言う問題があります。
本日ご紹介するのは、その薪について。
先日、春よりNPO法人【ふじ山 森の会】を立ち上げる代表の槇野和成氏が来社されました。
このNPOふじ山森の会は、
手入れが行き届かずに放置されている森林の間伐材を、
薪ストーブの薪に利用し、
燃やした灰を肥料に再利用することで、
富士山周辺の森林の保護・保全をしましょう、
と言う会です。
以前、和歌山の森のお話し(2/5〜8の記事をご覧下さい)でも触れましたが、現在日本の森林は非常に荒れています。
コスト的に成り立たない、と言うのが一番の理由です。
素人集団のNPOですから、まさか間伐の伐採作業は出来ませんが、せめて伐採した木を利用し、片付けや下草狩りなどを手伝えれば、富士山周辺の森林保護・再生に寄与出来、それは富士山周辺の土壌の保護にも繋がり、ミネラル豊富な地元の美味しい水つくりにも貢献出来るのでは…
そんな活動理念です。
作業を手伝った人で薪を分けあい、作業に参加出来ない人には安価で供給して行こう、と言うことだと思います。
私も、とても良いことだと思います。
今回来社頂き、薪ストーブに関する技術的な質問を受けると共に、
「何故薪の利用が二酸化炭素削減に貢献するのか?」
と言うご質問を頂きました。
私が直接研究したり、文献で調べたわけではないのですが、以前大学の先生のお話をお聞きしたので、そのお話を引用してご説明しました。
・木は、成長するときにCO2を大量に吸収する
・建材に適するような高樹齢材になると、CO2吸収量が減り呼吸による排出量が増える
(だから材木は使って新しく植林して行く方がよい)
・良い材木を作るには、材木に適さない材を間引く「間伐(かんばつ)」が不可欠
・間伐材はその場で放置するといつかは腐って朽ち果てる
・腐らせるのは微生物
・微生物も呼吸をするので、間伐材はそのまま腐らせてもCO2を発生する
・だから薪として利用して、燃焼でCO2を出しても、純増にならない
・逆に薪ストーブの利用で他の暖房エネルギーを減らした分、CO2排出量は減る
と言うことです。
この説明で納得して頂けたようで、喜んでおられました。
最近はNPOと言うと、とかく変な組織の隠れ蓑になったり、企業の金儲けに利用されたりしがちですが、代表の槇野さんが純粋に富士山と薪ストーブを愛しておられるのが、ヒシヒシと伝わったので、きっと良い活動に結びついて行くのでは、と感じました。
私も、微力ながらお手伝いが出来たらと思います。
会(まだ準備段階)と槇野さんのブログはこちらです。
→ふじ山森の会奮闘記
→マキ・薪・macky

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - リフォームのお話 > 薪ストーブのお話 | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
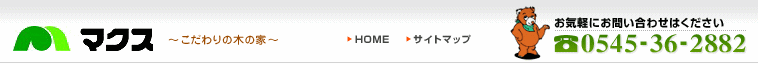

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 富士山と薪ストーブを繋ぐ【ふじ山 森の会】
マクス社長の住宅Blog
富士山と薪ストーブを繋ぐ【ふじ山 森の会】
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
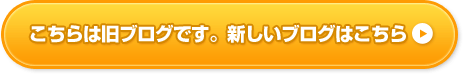

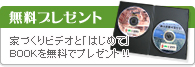


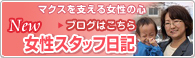




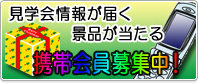

Comments