- 2008.09.30 火曜日
- 大工が使う道具には、一般的には聞かない名前の道具がいくつか有ります。
本日はその一つ「ががり」のご紹介。

以前ちょっとご紹介しましたが、只今会社の工場では、富士市の某神社の鳥居を制作中です。
桧ですが、なるべく腐らないように、加工後に防虫防腐剤を加圧注入します。
ですので、一階組んだものをもう一度ばらすので大変です。
上の写真は鳥居の上の部分を組んでいるところ。
丸太と丸太が合わさるので、接合部が三次元的に複雑になります。
また、薬剤注入で木が膨れるので、その分を見たり、その後の痩せを考えたりと、塩梅は将に長年の大工の感です。
でも、この様に加工後に注入することで、腐りやすい接合部にしっかり薬剤が入るので、持ちが違います。
ちょっと宣伝をすると、マクスのウッドデッキは、全てこの様に加工後の注入なので持ちが違います!
さて、施工中の現場にあるコレ。

コレが「ががり」です。
現在、鋸と言えば刃が使い捨ての、ワンタッチの鋸が使われます。
もっとも、プレカット化が進み、構造はおろか造作部分全てに至るまで出来合いの家も増えたので、電動丸鋸さえ有れば出来る家もありますが…。
また話題が逸れそうなので、話を戻します。
丸太を縦に挽く場合、その様なワンタッチの鋸では切れません。
やはりこの様な昔ながらの鋸が必要になります。
「ががり」は挽く時の音から来ているようですが、この大きな物を「おが」と言い(大鋸と書きます)、おがのクズだから、木のカスをオガクズ(大鋸屑)と言うのですね。
このががりは年代物です。

刃はもちろん大工が自分で研ぎます(目立て)。
不思議なことに、ワンタッチの鋸は、切れ味抜群ですが、一部分でも一度刃が飛ぶと、途端に切れなくなりますが、大工が研いだ鋸は、多少刃が飛んでも切れます(私がそんな気がするだけかも…)。


こちらは以前建てさせて頂いたお宅のリビングの梁を加工しているところ。
こんな風に仕上がりました。


是非守って行きたい技術・文化です。

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - 桧の家 住宅のお話し | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
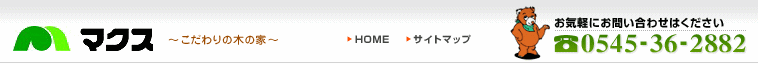

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > ががり
マクス社長の住宅Blog
ががり
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
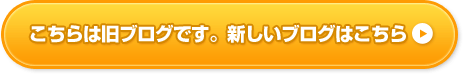

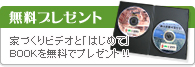


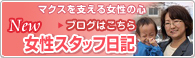




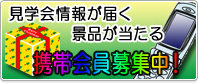

Comments