- 2007.06.18 月曜日
- ※ご注意 本日のブログ長いです。
さて、ティンバーフレームに使う8寸角の太い材料。そんなに太い無垢材は調整が必要では?乾燥は大丈夫?と質問されることがしばしばありますので、ちょっと長いですが書いてみましょう。
まず、木材の乾燥に関してですが、そもそも何故乾燥が必要なのでしょうか?
木材は、生きているので、伐採前には当然水分を含んでいます。木によっては、体重の半分以上が水分という木もあります。
木材は、乾燥をして行く課程で、収縮し、その収縮の度合いが部分的に異なりますので、曲がったりよじれたりします。
また、水分が多ければ、白蟻や腐りの原因の腐朽菌にも弱くなります。
そこで、品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)と言う法律で、構造材に関して表面含水率20%以下、と言う基準を設けています(日本の法律です)。
一昔前は、乾燥だ、含水率だと言う細かいことは言われませんでした。
それは、家造りがゆっくりとなされ、完成までに結構乾燥することや、真壁といって、いわゆる和室の柱が見えている造りのように、構造材を壁の中に閉じこめてビニールでくるむ、 と言ったことがなかった点が大きいと思います。
しかしながら、現在ではそのような工法が主流の為に、乾燥が重要になります。
乾燥が十分でないと、構造的なボルトもゆるみます。
リフォームで小屋裏に入ると、構造材のボルトは、殆どの家は手で回るくらいゆるんでいます。
その点、乾燥した材の寄せ集めですから、集成材は優れています。
ですので、現在の無垢の構造材に関しては、各社乾燥度合いにしのぎを削っています。
我が社は含水率○○%です!内部まで乾燥しています!
みたいな、お施主案の希望とはちょっとずれた宣伝を一生懸命しているのはちょっと滑稽だと感じますね。
乾燥によるメンテナンスが大変、と言う点で、一番分かりやすいのがログハウスです。
ログハウスは木を積み上げていますので、一本一本が収縮してくると、家全体の高さまで
変わってきます。
だいたい5cm以上建てた時より家が小さくなります。
「セトリング」と言いますが、この収縮を上から下まで貫通したボルトを使って毎年のように
締めて行き、ずれた柱に関しても、上部に付いたボルトで高さを調整します。
5年程度で落ち着きます。
大変ですね。
では、ログハウスは何で乾燥した木を使わない?と言えば、大経木の材料は、そもそも強制的に乾燥させること自体が難しいからです。
世界中どんな乾燥する釜(要するに温度を上げて強制的に水分を抜くわけです)を持ってしても、4寸角以上の木材を完全に乾燥させるのは困難なのが現状です。
また、この強制的に乾燥させる場合、自然に天日で乾燥させた場合と違い、「内部割れ」と 言って、表面が割れずに内部に大きな割れが出来、この割れがどういう訳か、柱の端部から覗くと向こうに光が見えそうなくらい連続して割れるのです。
これは直感的にまずいですね。
さて、乾燥に関して、マイナスのことばかり書きましたが、ここで話を戻しましょう。
そもそも、この含水率という法律が出来たのは、耐久性を担保する為の指針であることは
触れました。
乾燥していることの度合いとして、含水率計と言って、計器を木の表面に当てると、含水率が表示されるという非常に分かりやすい方法で、品質の基準を作ったわけです。
ただここに大きな落とし穴がありまして、そもそも、水分をどの程度含んでいるというのは、木によって大きく違うわけです。それを「20%」とか決めてしまった点に問題があります。
例えば、林に立っている木で、杉と桧の区別が付きますでしょうか?
好きな人は一目瞭然なのですが、一般の方は違いが分かりません。似ているからです。
でも、伐採して運ぼうとすると、大きな違いがあります。
桧は比較的軽いのですが、杉はもの凄く重いのです。
ところが、乾燥した製材は、杉は非常に軽く、桧は重いのです。
これは、杉の含水率がもともと非常に大きく、桧は比較的低い為です。
で、話が長くなりましたが、レッドシーダーはどうでしょうか?
オールドグロスと呼ばれる天然林のレッドシーダーは、極度に目が詰んでいます。
厳しい自然の中で生きてきたので、成長が極端に遅いのです。
使用する木材は、150年〜250年クラスです。
目が詰んでいると言うことは細胞も小さい、水分細胞も小さい、と言うことです。
そもそも極寒のカナダの森では、もし水分を多く含んでいては、凍裂と言って内部の水分が凍って膨張し、生きながらも割れてしまいます。
ですので、含水率が低いわけです。
マクスで使うレッドシーダーは、実は、乾燥させていません。
でも違法ではありません。
含水率計で計るとちゃんと20%以下です。
そもそもそんなに水分を含んでいない木なんです。
先週末、事務仕事をすっぽかし、会社を抜け出して現場へ…。
これは、チェーン・ノミと言う機械で、レッドシーダーの梁に、柱のホゾという部分がささる穴を開けています。

こんな感じで切りくずが出てくるわけです。これがまた良い香りだモンですから、ついつい現場に行っちゃうんですよね〜ぇ。やっぱ良いよなぁ…

でそれはさておき、前に書きましたが、柱のホゾは5寸有り、レッドシーダーの梁は8寸角ですので、この穴は、中心部まで十分達しているわけです。
でも、この切りくずを手に取ってみると…

あ〜ら不思議、乾燥してるじゃん、と言うと大げさですが、湿り気が随分少ない!
それだけ水分含量が低いって事の証です。
そして、水分が少ないだけでなく、腐りや白蟻に対して非常に強いので、法律の根拠の何故乾燥させなければならないか?と言う趣旨から考えると、機械で強制的に乾燥させる理由がありません。
では、割れや狂いは?
あります。
でも、松のように、指が入るような大きな割れは、細胞が小さく、収縮量が小さいレッドシダーにはおこらず、小さなヒビがいくつも入ります。
乾燥収縮でボルトがゆるまないか?
多分多少のゆるみも出るのでは?と思います。
ですが、ログハウスのように毎年それを締める必要があるという物ではないのはイメージ頂けるのではないでしょうか?
そもそも、ティンバーフレームの場合は、現在木造住宅の90%以上である機械加工のプレカットの様な、木を組まずに金物でくっつける家とは違います、
しっかりとした頑丈な仕口(接合部)で、組み上げるので、法的に金物は入れるのですが、
それはあくまでも補助的な物と私は考えています。
ですから、「むく材だから」、と言う特別なメンテナンスは必要ないと思います。
知り合いでも、お友達でも良いです。
木造で新築した方に聞いてみて下さい。
無垢の構造材で建てた家にはメンテナンスが必要で、乾燥した集成材で建てた家にはメンテナンスが必要ない、と言うことがあるでしょうか?
…そんなことはないですよね(笑)。
鈴木 - ティンバーフレーム 建築現場より | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
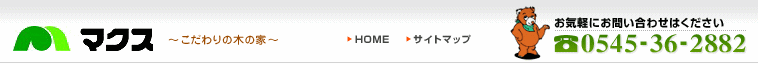

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > レッドシダーは乾燥材?
マクス社長の住宅Blog
レッドシダーは乾燥材?
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
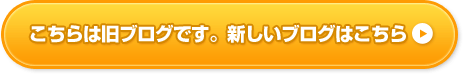

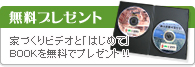


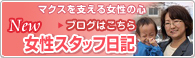




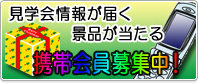

Comments