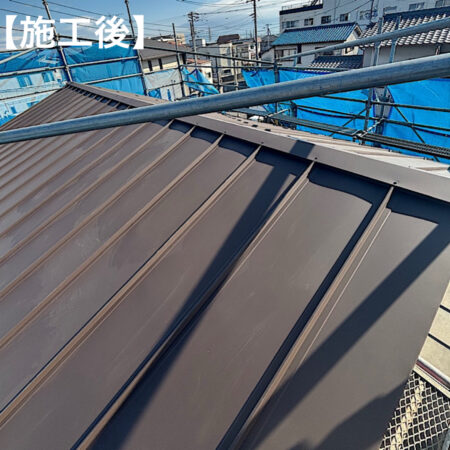昔からの技法…
おはようございます。社員大工の丸山です。正月休みから体調がどうも調子悪く、週明けから病院に行ってきました。 皆様もお気をつけください。
?先週末、体調も悪い中、弟弟子の会社の建前(建て方工事)の手伝いに行ってきました。
?昔も今も、建て方工事は大工にとって、一番の見せ場。ましてや、手加工ならなおさら。 弟弟子は、木取りから、墨付け、加工まで、自分たちの技術で仕上げてきました。
?今の時代は”プレカット”と呼ばれる、木材加工技術が普及し、こうした昔ながらのやり方は、珍しくなってきました。 色々な技法が施されてましたが、その一つが”金輪継ぎ”と、呼ばれる継ぎ手。 継ぎ手の中でも最高ランクです。
?写真では分かりづらいかも知れませんが、真ん中にある、”楔(くさび)”が斜めになっており、上から叩くと両材が引き寄せられる、という大工でも加工が難しく手間もかかる継ぎ手。 弟弟子は、継ぎ手を全部、金輪継ぎにしてました。
?そして、こんな事も。
?建て方中でしたので、写真が上手く、 撮れてないのですが、古来からの技法の1つ、”渡りあご工法”と言う工法で、建てられてます。(気になる方は調べてください)
この工法は、梁と桁とが交互に重なりあうことで、強度を出しています。 昔から地震に強い造りになっています。
?ですが、こうした技法や工法も、今の建築基準を満たすには、金物を付けろだとか、耐力面材を貼れだとかしなければ、書類も検査も通らない時代になってきてしまいました。 時代の流れなのか、仕方がないことなのか、大工の”見せ場”が、無くなる事は、寂しく思います。
2016年01月12日
Post by 丸山 彰
About Me

胸を張れる仕事しかできません。ブログでは、仕事ぶりや自分達も家に住み生活しているその様子も何かの役に立つかと思いブログに綴ります。
現場監督ブログアーカイブ
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (6)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (8)
- 2024年7月 (6)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (7)
- 2024年4月 (10)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (10)
- 2023年9月 (14)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (7)
- 2023年5月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (6)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (11)
- 2022年9月 (7)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (7)
- 2022年2月 (8)
- 2022年1月 (10)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (10)
- 2021年6月 (6)
- 2021年5月 (3)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (8)
- 2021年1月 (8)