- 2009.06.30 火曜日
- 築地松(ついじまつ)というのをご存じでしょうか?
名前は知らなくても、TVで↓こんな風景を見たことはありませんか?

本日もミニ建物探訪で、島根の出張での一コマです。
昨日に続いて、その土地ならではの街並みについて書いてみようと思います。
最初の写真は、散居村と呼ばれる風景です。
家のまわりが水田で、各家と家は、約100mほど離れて分散している集落を言います。
ちなみに、日本三大散居村は、ここ島根の出雲平野と、
富山の砺波(となみ)平野、
岩手の胆沢平野
だそうです。
さて、
築地松とは、出雲平野における、この独特の生垣です。
生垣と言っても、高さは8mから、高いものでは12mにも達し、当然家の屋根よりも高くなります。

私たち静岡県民にとって、この常識を外れて背の高い生垣。
冬の強い季節風と、台風の風を防ぐもの、なのは容易に想像出来ます。
が、
大風は日本中どこでも来るし、沖縄の石垣ように台風銀座でもないし、
「何もそこまでしなくても…」
と前から思っていました。
その疑問は今回解けました…(後半に)。
朝日新聞の「にほんの里100選」にも選ばれているこの築地松。
今回見学させて頂いたのは、地元島根県斐川町で築地松ボランティアガイドを務められる瀬崎さんのご自宅です。
さぞや暗いのでは?
と思っていましたが、瀬崎さんのお宅に案内して頂くとこの通り。

実は、生活には全く支障がなく、普通に明るいのです。
家側に伸びる枝は皆剪定され、高さもキレイに揃っています。
この剪定作業は、陰手刈り(のうてごり)と地元で呼ばれる作業で、適度な風通しと採光を得、田畑が陰になるのを防ぎ、松食い虫を予防し、伸びすぎた枝が風で折れないようにする、
そして何より美しく切りそろえることが目的で、高所での作業で、命綱も付けずに、木から木へと作業をするそうです。
しかも驚くことに、庭木の剪定で一般的になされるように、縄を張って高さを揃えて切るのではなく、目見当でビシッと高さを揃えるのだそうです。
いやはや、熟練の職人技って凄いですよね。
築地松は現在は黒松が主なのだそうですが、実際によってみると、その太さにビックリ!

ほらっ!
だいたい瀬崎さんのお宅で樹齢150年以上だそうです。
また、恥ずかしながら知らなかったのですが、この築地松は、風を防ぐだけではなく、他にもまだまだ大きな役目があるのです。

この様に、家は盛り土で一段高くなっており、河川の増水時に浸水するのを防ぎ、同時に強い根で土地が流されるのも防ぐのだそうです。
そしてさらに、この太い松は、家の基礎の下深くにがっしりと根を張り、地盤が弱いこの地方の家が、不同沈下をするのも防いでいる、つまり木の根の浮き輪で家が沈まない役目も果たしているのだそうです。
すっごいですね〜っ!
先人の知恵です。
築地松は、どの家も、建物の北側と西側のみです。
冒頭の「大風はここだけではないのに?」、という話ですが、実際にこの地に立ってみると、まるで築地松のある出雲大社の方角から轟々と吹いてくる風の流れが見えるような地形で、なるほど、強い卓越風が昔からあったからこそか、と感心したのでした。
先週も書きましたが、その地にはその地のデザインがある、
まさにその見本のような美しい風景なのでした。

↑自然素材を扱う工務店のブログが集まってます【日本ブログ村】 - ミニ建物探訪 | comments (2) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
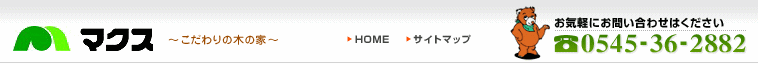

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 築地松(ついじまつ)
マクス社長の住宅Blog
築地松(ついじまつ)
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
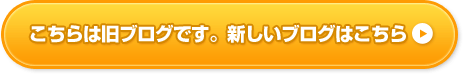

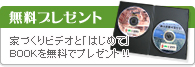


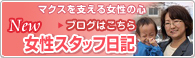




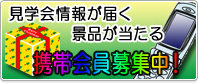

Comments
まったくでございます。
勉強しても勉強しても知らないことばかり。
まして、コンピューターも精密測量機器もなかった時代の知恵が、現在の建築技術を簡単に凌駕するのを見せつけられると、昔の人はエラかぁ〜、と思うばかりです。
出雲は神様が集まる場所ですから。
築地松はすごかですね。
100年の時を経た剪定方法がまるで
網を張ったように見えます。
松が家の基礎をささえているのか。
歴史を感じられるお住まいです。