- 2008.02.05 火曜日
- 昨日の予告の通り、和歌山での森のお話しをご紹介致します。

隠すつもりもないのと、先方に許可を頂いたので、訪問先をまずはじめに記します。
今回視察に行ってきたのは、和歌山の株式会社山長商店さん。
何と山手線の内側と同じ面積の森を持つという林業家です。
今回案内して頂いたのは、紀州の山を知り尽くした林業部長の松本さん。


優しい紀州弁の語り口からは、木への、森への優しさが自然と伝わってきました。
今、盛んに言われている言葉に、地産地消と言う言葉がありますね。
地場のものは地場で消費するのが一番、と言う考え方です。
多分、もとは食から出た考え方だと思うのですが、材木についても、地元材、と言う言葉とセットで使われています。
この考え方に力を貸すのは、名工と謳われた、宮大工の故西岡棟梁が遺した「大工の口伝」からの抜粋です。
〜地元の木を、方向までそのままに使いなさい〜
と言う様なことを言っているのですが、前後の文をよく読むと、地元の木以外を使ってはいけないとか、生えていた向きをそのまま使えとか、そんなことを言っているのではないことは、すぐに分かります。
話が逸れましたが、何を言いたかったのかというと、家造りにおいて、
「材木は、地場のものを使うのがベストか?」
と聞かれれば、私は躊躇なく
「NO!」
と言います。
これは明らかに地産地消という概念からは逸脱しますが、例えば、私たちの地元の富士桧、木が好きな人間としては非常に残念ですが、決して良い材料ではありません。
むしろ、木造建築構造材としての評価はかなり低い方だと思います。
富士の桧が悪いのではなく、建築構造材として、と言う意味です。
お断りしておきますが、富士桧で建てた家が、すぐ潰れるとか、そんなことは全くありませんし、そんな事は微塵も思っていません。
ただ、より丈夫に、より耐久性が高く、と言う様に考えた場合に、と言う意味です。
コストパフォーマンスや、地元の産業育成、輸送コスト節約や輸送CO2削減と言ったメリットはもちろんあります。
ただ、名前だけのブランドイメージで宣伝・営業し、本質をお伝えしないことは、やはりいけない事だと思いますので。
さて、話しを紀州に戻しますが、上記の事は今回、構造材料として全国的に定評のある紀州の山、そしてそこで木を育てる人々と話すことで、再認識したことです。
今回、伐採現場から見てきたのですが、



やはり何と言っても一番違うのは、年輪です。
つまり、年輪の幅が狭い、目の良く詰んだ材である、と言うことです。
今回知った部分が大きかったのですが、この目が詰んでいる・いない、と言うのは、単純に気候の寒暖によって、成長に差がある、と言うのではなく、
「その様に育てる」
ものであると言うことでした。
例えば、よく目の詰んだ材の代名詞である、吉野材。
これは、元々桶を作るために、水が漏れない、極度に目の詰んだ、きめの細かい材木の必要から作られたものであること。
また、九州では、造船が盛んなことから、船の材料として、とにかく大経木が必要だったからその様に作られたものであること。
この様に、元々の材の仕様目的によって、その産地の木の性質は、先人の努力によって、作り上げられて来たものであったわけです。
そして、この紀州の森は、木の国という名に相応しい、まさに構造材のために作られてきた森でした。




いかがでしょうか?
何て美しい森でしょう!
何度も書きますが、この森は、50年〜100年という時を経て、手をかけ、愛情をかけ、守られ、作られて来た森なのです。

そして、その森から集積される材は、この様に、目の詰んだ、強度と光沢があり、色が良く、狂いの少ない良質な構造材になるのです。

長くなってしまいました。
次回は、どの様にしてこの森を造り、守って行くのかを書いてみようと思います。 - 桧の家 住宅のお話し | comments (0) | trackbacks (0)
静岡県富士市でこだわりの木造住宅を建てるなら株式会社マクスにおまかせください。
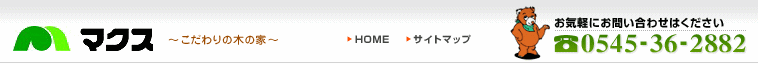

HOME > マクスの社長Blog 頑張れ四代目日記 > 紀州の森
マクス社長の住宅Blog
紀州の森
Trackbacks
この記事のトラックバックURL:
株式会社マクス 〒417-0801 静岡県富士市大渕3256-2 TEL : 0545-36-2882 FAX : 0545-36-2284 E-mail : tokoshie@macs-inc.co.jp
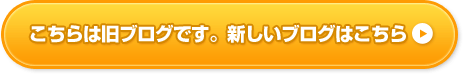

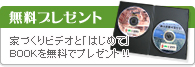


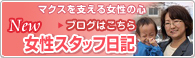




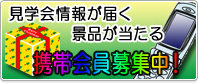

Comments